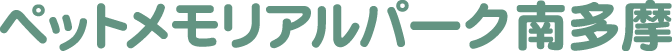ハロウィンといえば仮装やお菓子。
でも実は、もともとは“亡き存在を迎える供養の行事”だったってご存じでしょうか?
にぎやかなイベントのイメージからは想像しにくい、ハロウィンのルーツをのぞいてみましょう。
ハロウィンの起源は「サウィン祭」
ハロウィンの起源は、古代ケルト民族の「サウィン祭」。
秋の収穫を祝いながら、祖先の霊を迎える日とされていました。
この日は生と死の境目がもっとも近づくと考えられ、先祖の霊だけでなく悪霊もやってくると信じられていたのです。
そのため人々は――
- 仮装:悪霊から身を守りつつ霊を迎えるための装い
- お菓子:霊や妖精に供える供物
として過ごしていました。
つまり、仮装やお菓子配りはもともと「供養の一部」だったんですね。
日本のお盆・彼岸との共通点
日本にも、先祖を迎える行事があります。
夏のお盆や、春と秋のお彼岸。
静かに迎えるお盆、にぎやかに彩るハロウィン。
スタイルは違っても、「亡き人を大切に想う心」は世界共通です。
ペット供養への小さなヒント
ペットを偲ぶときにも、ハロウィンの明るい彩りをヒントにすることができます。
- オレンジや紫のお花を供える
- 小さなキャンドルを灯す
- 思い出の品をハロウィン風に飾る
ほんの少し雰囲気を変えるだけで、しめやかな供養とは違う、温かくやさしい時間が生まれます。
まとめ
ハロウィンはただの仮装イベントではなく、もともとは「供養の行事」。
日本のお盆や彼岸と同じように、大切な存在を想う日だったのです。
今年のハロウィンは、にぎやかな街のイベントを楽しむだけでなく、愛する存在を想い出すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。