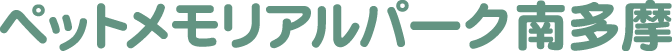お彼岸はご先祖を供養し、亡き人を思い出す大切な時期です。近年では、ペット霊園や法要に参加して「家族の一員」としてペットを供養する方も増えてきました。
でも実は、ペットを供養する文化は現代に生まれた新しいものではありません。日本の歴史をたどると、驚くほど昔からその痕跡が見えてきます。
縄文時代に行われていた犬の埋葬
青森県の三内丸山遺跡では、人と一緒に犬が丁寧に埋葬されていた跡が発見されています。
このことから、犬は単なる狩猟のパートナーや家畜ではなく、「家族」として扱われていた可能性が高いと考えられています。
江戸時代にもあった犬猫のお墓
時代が下って江戸時代になると、庶民の間でも犬や猫のお墓が作られていました。
「ペット」という言葉はまだなかったものの、人々は身近な動物を愛し、亡くなればきちんと弔う文化を自然に持っていたのです。
「ペット」という言葉の由来
英語の pet は「撫でる」「可愛がる」という意味から派生し、19世紀ごろには「愛玩動物」を指すようになりました。
日本には明治時代にこの概念が入ってきて、やがて「ペット=家族の一員」という考え方が広がっていきました。
昔も今も変わらない「絆」
こうして見てみると、ペットを大切に思い、供養する文化は決して新しいものではなく、縄文時代から続く人と動物の絆の表れだと言えます。
お彼岸という節目に、改めて愛するペットを思い出し、静かに手を合わせる時間を持つのも良いかもしれません。